コラム
column
2024-11-24
“The Missing Billionaires”を読んで
“The Missing Billionaires”(著者 Victor Haghani, James White)を読了しました。ここ数年読んだ本の中で最も考えさせられ、感銘を受けたため、紹介いたします。内容は確率などの数学を使った金融理論ですが、実用的で広範囲のビジネスの意思決定に適用できるものです。
1877年時点で世界一の金持ちであったVanderbilt氏。その遺産を相続した一族のその後を見ると誰一人として億万長者リストに残っていない。安全資産(国債など)とインデックスファンドにでも投資し、それなりの節度を持って生活していれば、Vanderbilt家から10億ドル(現在の為替で1,500億円)をこえるBillionaireが何十人も出ていてしかるべきだ。むしろBillionaireにならない方が難しいのではないか。何が起こったのか?彼ら、彼女らは最適なリスクを取ること、つまり大きすぎず、小さすぎないリスクテイクに失敗しており、この最適なリスクテイク、投資のサイジングを意識し実行していくべきだというのが本書の主張です。
<Missing Billionaires>
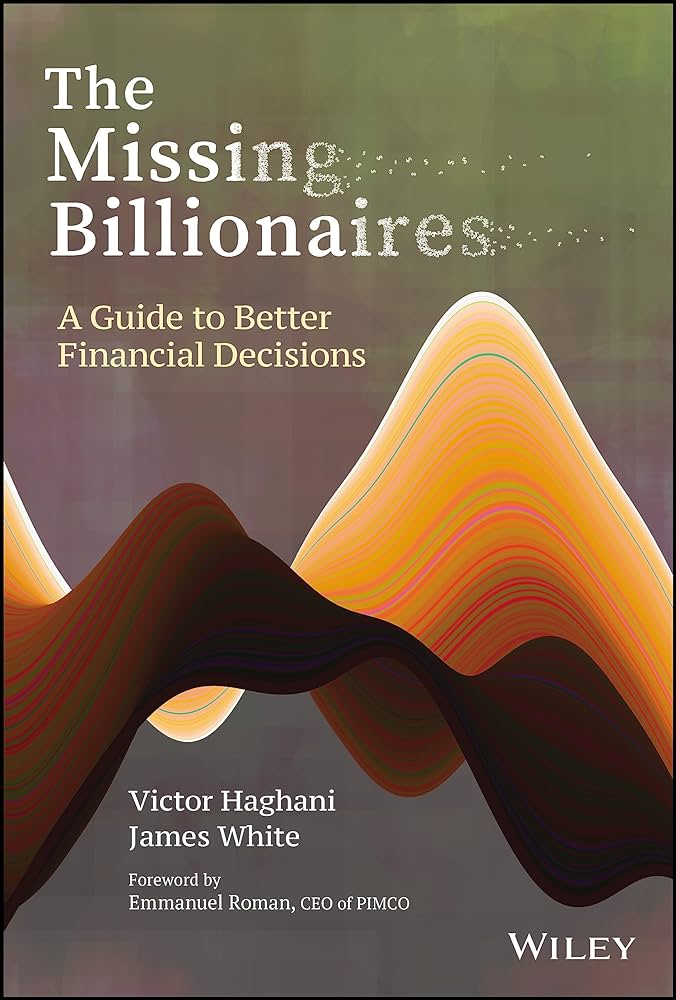
まずは以下の事例での問いかけがあります。
今、25ドルが手元にある。コインがあり、そのコインを振ると60%の確率で表、40%の確率で裏が出る。ここで賭けを行う。表か裏か当てられた場合は賭けた金額の2倍を得ることができる。5ドルかけ、当たれば倍になり10ドルもらえ、5ドル増えることとなる。3ドルなら6ドルとなる。賭け金額、表か裏は自由に設定できる。制限時間は30分(300回程度賭けることができる)。残った金額はもらうことができ、最大250ドル。ドルがなくなれば終了。(解答は示しませんので、答え合わせは本書を購入ください。)
ギャンブルでよく言われることは、負けるたびに賭け金を2倍ずつ増やし続けることですが、どこかで運悪く破産してしまう(掛金がなくなってしまう)ので最適解ではありません。この事例で示されるのは、自分の利益を最大にする最適な賭け方があるということです。それは小さくかけたら負けはしないが、意味のある金額に達しない。大きすぎたらゼロになるリスクが高まります。
この事例からスタートし、現代ポートフォリオ理論(Modern Portfolio Theory(MPT))の改善方法を示しています。MPTとは金融資産ポートフォリオで債券、株式、不動産REITなど資産の相関係数を見る中、組み合わせることで価格変動リスク分散を抑えながら最大の収益を上げるという考え方です。
本書では最小の分散で最大の収益をもたらすポートフォリオ最適化やシャープレシオ分析では不十分で、最適なリスクを取ることにならない。効用関数(Utility Function)を組入れるべきと主張しています。
効用関数とは、簡単にいえばポートフォリオ資産の増加・減少により感じる効用のことです。資産は増えるほど効用は上昇するが、限界効用は低下します。しかし、減少すると効用は下がり、さらに下がるほど限界効用の下落は大きくなる。例えば、資産家がずっとあこがれていたプライベートジェットを購入する場合、1台目は購入時大きな喜びを感じるでしょう。2台目を購入する場合はうれしいでしょうが、1台目ほどの満足は得られないでしょう。3台目もうれしいでしょうが、2台目よりも満足度の増加は少ないでしょう。4台目は・・・となります。限界効用は減少することになります。
反対に資産が減少する場合はどのようになるでしょうか。10億円のポートフォリオがあったとして、半分の5億円に減少したら、不愉快で気分が悪い(効用は減少する)でしょう。さらにその半分の2.5億円に減少したら10億円から5億円に半減した時よりもさらに不愉快度は増すでしょう(限界効用の低下が激しくなる)。
このような、満足度、不愉快度などを効用関数として組み込んで、アップサイド、ダウンサイド発生の確率を反映した効用を最大化すべく、リスクテイクを最適化すべきと提言しています。本書では効用を組み込んだ利回りをRisk Adjusted Returnと呼んで数式化し、各種数値をアンケートや面談などで実証的に示しています。安全資産とリスク性資産と2つのアセットクラスのみですが、以下の数式などは極めて実用的です。
RAR(Risk Adjusted Return)=rrf+k(μ-k*γ*σ^2/2)
rrf :安全資産収益率
k :リスク資産への投資割合
μ:超過収益率(リスク資産収益率ー安全資産収益率) 一般に3~6%とされる
γ:相対的リスク回避度 一般に2~3。
σ:収益率の標準偏差 株式など一般に15~20%とされる。
ここでは、金融ポートフォリオに主眼をおいた記述になっていますが、実際のビジネスもリスクテイクですので、応用が可能で、私のコンサルティング活動にも組み込んでいきたいと考えています。私はイギリスでMBA修了、CFA(米国の証券アナリスト)なども保有していますが、本書で主張される最適な投資サイジング、リスクテイクのカリキュラムに出会ったことがありません。クロスボーダー、国内M&Aに関するコンサルティングなどに従事しましたが、この点は心の中で気にはなっていたものの、明示的にアジェンダとして挙げることはなかったです。
たとえば、以下のような応用が考えられます。
・海外事業を考えているが、事業調査などを行ったところ、大きなビジネスになるポテンシャルがある一方、ゼロになる可能性がある。経営者が50億円の資産がある。この事業は規模が大きく、求められる資本も大きい。どこまでなら資本供出できるか。さらに外部から資本を入れることで成功する確率は高まるが、自分の持ち分は希薄化する。どちらを選ぶべきか?
・会社が成長しIPOを行うことになった。創業者持分は数十億円ほどの価値になりそうだが、創業者資産の90%以上を占めることになる。IPO後しばらくは株価が跳ねそうだが、創業者はロックアップ期間があり、IPO後1年間保有し続けなければならず、好きな時に売却できない。会社の先行きには自信はあるが、金融市場の変動もあり、IPO株式は大きな変動が予想され、大幅な下落に見舞われることも念頭に置かねばならない。創業者はロックアップ期間終了まで保有すべきか、もしくはIPO時に売却すべきか、売却する場合、どの程度の持分を売却すべきか。
などです。新しいコンサルティングテーマとして研究を重ねたいと考えています。
